老犬が薬を飲まない…と悩む飼い主さん必見。体験談から見えた「飲ませるコツ7つ」と、飼い主もイライラしないための心の持ち方を徹底解説します。
愛犬が薬を飲まなくてつらい…そんな経験、ありませんか?
老犬になると、病気の治療や予防のために薬を飲む機会が格段に増えますよね。
フードの上に錠剤をポンと置けば、パクパク食べてくれる子もいれば、お薬だけ上手によけてしまう子もいます。
「何をどうやっても飲んでくれない…」と悩む飼い主さんも多いでしょう。
何を隠そう、我が家の愛犬も、薬は本当に苦手で、飲ませるのにあの手この手で工夫していました。
この記事では、薬をすんなり飲んでもらうために飼い主さんができることを、私が愛犬に薬を飲ませる時に工夫したことを交えてご紹介していきます。
具体的には、「自分でごはんを食べられる時期」「介護が必要になった時期(寝たきりに近い状態)」の2つの時期別に実際に効果があった方法を、体験を交えて詳しく紹介します。
さらに、飼い主のストレスを軽減する心の在り方についても深掘りしています。
老犬が薬を飲まない3つの理由
老犬が薬を嫌がる、飲んでくれない主な理由は3つあります。
- 不味い。変な匂いがする。
- 飼い主さんのイライラや緊張が愛犬に伝わってしまっている。
- 薬を飲ませる時に、飼い主につかまって動けなくなったり、マズルを触られるのが嫌
一つずつ、詳しく書いていきますね。
1. 不味い。変な匂いがする。
犬の嗅覚は人の約10,000倍も敏感といわれています。
人間が「無臭」に感じる薬でも、犬にとっては「苦い」「酸っぱい」「薬っぽい」といった匂いが強く出ていることが多いです。

いつもと違う匂いはすぐわかるよ
特に、粉薬はその細かな粒子ゆえに匂いが飛びやすく、フードごと拒否される原因になります。
ですから、人間には匂いを感じなくても、「全くの無臭、ということはないだろう」という前提で薬を飲ませる工夫が必要になります。
加えて、薬は不味いものです。多少甘味がある薬もあるようですが、それでも愛犬には不味く感じる可能性がある、と考えましょう。
人間は、多少苦い薬でも、飲んで治るからガマンする、という考え方ができますが、犬には薬を飲む必要性は理解できません。
ですから、変な匂いがしたり、不味いとわかっているものは飲みたくなくて当然なんです。
2. 飼い主さんのイライラや緊張が愛犬に伝わってしまっている。
薬は処方された量をちゃんと飲ませる必要がありますよね。
だから、飼い主さんは「お薬飲ませなきゃ」と知らず知らずに肩に力が入ってしまうものではないでしょうか。
「ちゃんと飲んでくれるかな」とか、いままでうまく飲んでくれなくて吐き出されたりしたことがあると、「また飲まないんじゃないか?」と思ってしまいます。
こういう気持ちは、全部愛犬に伝わってしまうんですよ!

大好きな飼い主さんの気持は、全部わかっちゃうわ
アニマルコミュニケーションをやっていて実感しているのですが、犬は飼い主さんの気持ちや感情を本当に敏感に感じ取ります。
薬を飲ませるときの、いつもと違う飼い主さんの気持ちや感情を察して、犬は警戒してしまうんです。
我が家の愛犬も、私が薬を準備し始めると、あっという間にケージの中のドーム型のベッドに入ってしまい、出てこないことがよくありました。
さぁ、薬の時間だ!飲んでもらわなきゃ!」という気持ちを察していたんだと思います。
3. 薬を飲ませる時に、飼い主につかまって動けなくなったり、マズルを触られるのが嫌
薬を飲ませる時に、よくあるやり方が「口を開けさせて中に錠剤を入れる」というやり方です。
粉薬の場合は、ごく少量の水で練って老犬の頬っぺたの内側に擦り付けるやり方があります。
この時、顔やマズルを触られるのに慣れていないと、とってもイヤなことをされていると感じる子が多いんです。
我が家の愛犬はマズルを触られるのが本当に苦手で、トリミングも歯みがきもなかなかさせてくれない子でした。
小型犬なのに抱っこもキライで、抱っこして飲ませようとすると暴れて逃げ出すこともしょっちゅう。
そのため、水で練った粉薬を愛犬の頬っぺたの内側にくっつける、なんてとてもじゃないけど無理!という状態でした。
普段からもっと、抱っこや顔周りを触れることに慣れさせておけば良かったな、と反省したものです。
老犬の段階別:愛犬に優しい薬の飲ませ方7つの工夫
老犬の薬の飲ませ方は、その子の体調や介護の進行度合いによって柔軟に変えていく必要があります。
ここでは、活動的な「自分でごはんを食べられる時期」「介護が必要になった時期(寝たきりに近い状態)」の2つの段階の特性を考慮し、7つの工夫をご紹介します。
自分で食事が食べられる子への工夫
この時期の老犬は、まだ活発に動き、自分で食事を摂ることができます。
薬を嫌がるのは味や匂い、あるいは飼い主さんの緊張が原因であることが多いでしょう。
✅ 1. 食事前の空腹時に投薬
薬の消化吸収効率を考えると「食後」が望ましいですが、老犬が薬を頑なに拒む場合は「空腹時」も有効です。
我が家のごはんの時間は、朝の6時と夕方6時の1日2回。1日1回だけ飲ませる薬は、夕飯前に飲ませることが多かったです。
我が家の愛犬は多頭崩壊からの保護犬で、ご飯を食べることが何よりの楽しみだったんです。
だから、お腹が空いていて食べたい気持ちが高まっているときだとうまく飲んでくれることが多かったです。
特に高齢になると「お腹が空いている感覚」が希薄になってきますので、「おいしいごはんの直前」というタイミングを狙うのがコツです。
✅ 2. カボチャ/サツマイモで錠剤を包む
我が家の愛犬は、錠剤をフードに混ぜると、薬だけ器用に残してしまいました。
粉薬をフードにふりかけたり、混ぜたりすると、ご飯を残すこともありました。
普段の食事を嫌がるようになったら困るので、我が家の愛犬にはフードに混ぜる方法は合っていないと判断しました。
そこで、別アプローチとして柔らかい芋系で包む方法を採用しました。

サツマイモ大好き!甘くておいしい!!
茹でてつぶしたカボチャやサツマイモは自然な甘みと舌触りがあり、薬も包みやすい素材です。
【薬を飲ませる手順】
- ① 薬なし団子を2〜3個与え、警戒を緩める
- ② 薬入り団子を与える
- ③ 最後に薬なし団子を数個追加し、ご褒美ムードで終了
この順序があるだけで、「え?今の何?」という驚きや疑いをそぎやすくなりました。
犬用のチーズにはさんで飲ませる、という方法も試しましたが、チーズから錠剤がポロっと外れてしまい、ことごとく失敗してしまうんです。
錠剤全体をすっぽり包めるようなものを使うのが、うまく薬を飲ませるコツだ、と学びました。
✅ 3. 粉薬は無糖ヨーグルトで即ミックス
粉薬だけではすぐにバレてしまうため、「あの匂い」が強すぎないヨーグルトを使用します。混ざった瞬間に舐めさせれば、匂いが広がる前に口に入れてくれました。
無糖のヨーグルトが大好きだったので、粉薬をヨーグルトに混ぜ、時間をおかずに愛犬に食べさせるとキレイに食べてくれました。
【注意点】
- 無糖タイプを選ぶ(砂糖の入ったものは避けて)
- 混ぜてすぐ、30秒以内に与える(時間を置くと、ヨーグルトと薬が反応して味が変にならないか?という心配があったので、混ぜたらすぐにあげるようにしました。)
- ヨーグルトが苦手な子には豆乳ヨーグルトなど代替品も試して

私はヨーグルト派よ!
✅ 4. ペーストおやつの活用(相性重視)
液状・ペースト状で薬を混ぜられるものも多数ありますが、愛犬との相性が重要です。
チーズでは薬が滑ることがあり、うちはペースト系おやつ(スムージー・犬用ミルクペーストなど)も候補に入れました。
ペースト状のオヤツやごはんに混ぜる方法も試しましたが、我が家の愛犬はヨーグルトが一番うまく飲んでくれたと記憶しています。
実際に複数の商品を小ロットで試し、「薬入りでも違和感なく完食できたもの」をストックするのがおすすめです。
食事介助が必要な時期の子への工夫
この段階の老犬は、自分で食事を摂ることが難しくなり、飼い主さんによる食事介助が必要になります。
投薬も身体的な負担を考慮し、より慎重に行う必要があります。
✅ 5. 果汁やスープ+シリンジで投与
寝たきり近くなると食事介助が必要ですが、この時期に最も効果があったのは「果汁」「肉の煮汁」「野菜スープ」+粉薬を溶かす方法でした。
シリンジを使って少量ずつ流し込むと、犬の負担が少なくなります。
若くて元気なころは、水や果汁に粉薬を混ぜてもザラっとした感触があって嫌なのか、全部飲まずに残すことがほとんどだったんです。
ほとんど寝たきりになってからは、水分補給もかねて果物の果汁やお肉のゆで汁に粉薬を混ぜて飲ませました。
シリンジに入れた薬を嫌がって、顔をそむけるようなことも何度かありましたが、根気強く、少しずつあげていくと、全部飲んでくれましたよ。
【ポイントは以下のとおり】
- 高齢期に多い脱水予防にスープが好まれる
- 冷ましすぎない(人肌程度)
- 嫌がる場合は少量ずつ、リラックスした声かけも効果的。
- ほんの少しでも飲んだらベタ褒めすると、その気になってくれることも
飼い主さんの心構えと獣医師との連携
どちらの段階においても、飼い主さんの心の持ち方や、必要に応じて獣医師との連携を図ることは非常に重要です。
✅ 6. 獣医師に調剤方法の変更を相談
犬に処方される薬には、錠剤、粉薬、シロップ、カプセルなど調剤方法はいくつかあります。
一般的に、獣医は患者(犬)や飼い主の事情を踏まえて、薬の形を変えてくれることがあります。
薬の種類によっては、「錠剤は飲めないので粉薬にしてください」というリクエストができることがあります。
錠剤やカプセルは、フードでくるんで飲ませる方法がとりやすいので、比較的飲ませやすいと思います。
粉薬は、愛犬が口の中に指を入れても嫌がらない子であれば、頬っぺたにこすりつけて飲ませる方法が確実です。
または、水やだし汁に混ぜて飲ませるとうまく飲んでくれる子もいますし、既に介護状態でシリンジを使っているなら、シリンジで飲ませるとやりやすいです。
逆に「粉薬だと苦いみたいなので錠剤にできますか?」とリクエストすれば、相性の良い剤形に変更してもらえるケースもあります。
【自分で錠剤を砕いたり、カプセルを開けて飲ませていいの?】
動物病院で処方される薬が錠剤だったり粉薬だったりするのは、それぞれの薬の効果や効く時間の長さなど、必ず意味があります。
砕いても問題ない種類の薬もありますが、処方された錠剤を砕くと効果が減ったり、薬が効いている時間が変わってしまうこともあるんです。
カプセルは開けた中の薬はとっても苦い!ということもあります。
錠剤を砕いていいか、カプセルを開けていいかは、必ず薬を処方した獣医師に相談してくださいね。
✅ 7. 飼い主の心構えを「知恵比べ」に切り替える
私が最初に大きな変化を感じたのは、「投薬=遊び感覚」に切り替えたときでした。
薬を飲んでくれないとき、イラッとしてしまうことがよくありました。
なんで飲んでくれないの?飲めばラクになるんだよ?飲まないとダメなんだよ?
でも、そんな風に思うほど、愛犬は薬を嫌がって飲んでくれないんですよね。
記事の最初に書いたように、犬は薬を飲む意味を理解できないものです。
だから、飲んでくれないのが当たり前。薬を準備しながら、深呼吸してリラックスにつとめました。
そして、「どんな方法ならうまくいくかな?」と愛犬と楽しく知恵比べをしているような気持ちを持つようにしていましたよ。
飲まないときは、「私より知恵があったか!」と感心してみたり、後でまたチャレンジしてみればいいや、と少し気軽に考えるようになりました。
そうすると、不思議なことにすんなり飲んでくれることも増えたんです。
飼い主の心を軽くする3つのポイント
- ① 自分に「完璧じゃなくていい」と許可を。 少しの失敗も「愛情を尽くした証」。
- ② 調剤替えや訪問介護・ペットシッターの利用も一手。 一人で抱えず、頼ることも飼い主としての賢い選択。
- ③ 緊張をほぐす工夫として、深呼吸・音楽・短い休憩も導入。
まとめ|愛犬と飼い主、両方に優しい投薬を目指して
まだまだ元気な時期から介護期まで使える7つの工夫と、心のケアをバランス良く取り入れることで、薬を飲むタイミングが苦痛ではなくなってきます。
愛犬が穏やかに、そしてあなたも穏やかに投薬タイムを迎えられますよう、心から応援しています。
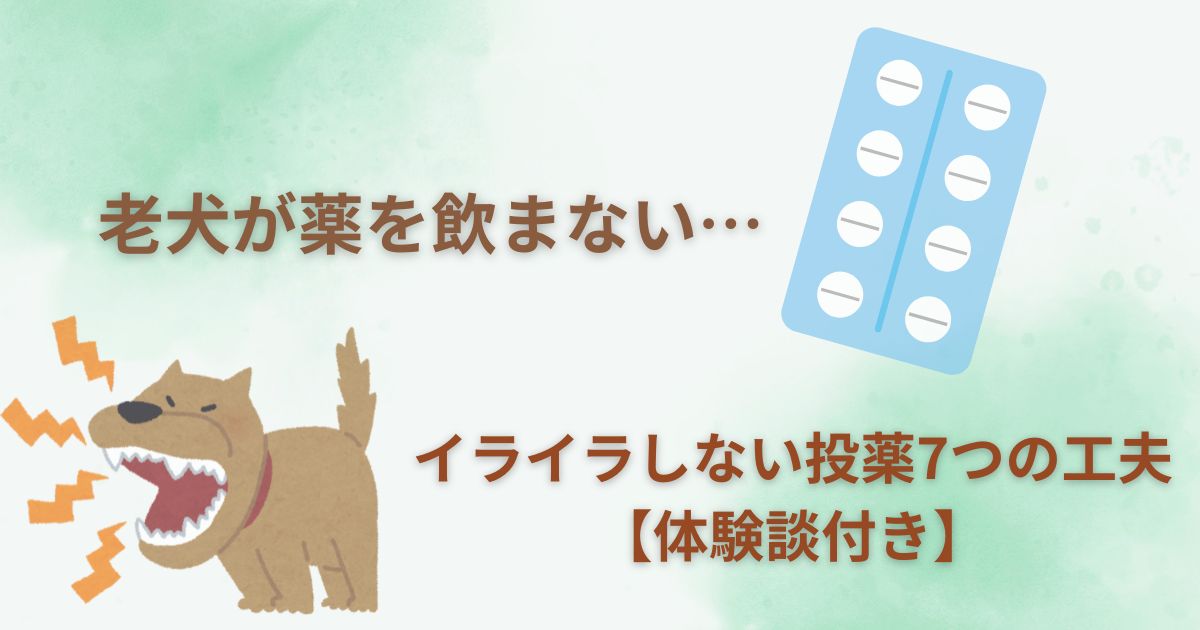


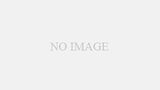

コメント